本で調べる東京名所 永田町・霞が関編
江戸の町. 上 (巨大都市の誕生)新装版(日本人はどのように建造物をつくってきたか)
内藤昌 著, 穂積和夫 イラストレーション 草思社 2010.10
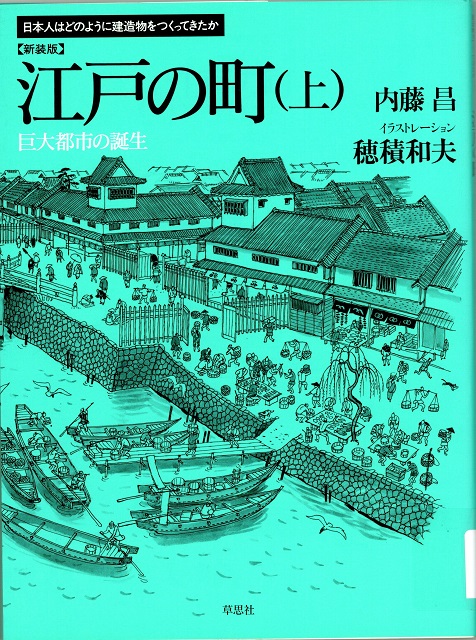
この本は江戸城築城以前の江戸の原風景、太田道灌(おおたどうかん)[?]の江戸城築城、徳川家康の江戸城入城から明暦の大火までの約70年間を豊富なイラストを交えて描いています。
徳川家康は平安京をモデルにし、四神相応 (しじんそうおう)[?]の原理に基づいて都市計画を立てました。その後、家康は江戸に幕府を開いたことで、江戸の町を更に大きく発展させる必要がありました。
そこで江戸城を核にして、これまで作ってきた町をそのまま利用し、自然の地形を生かして「の」の字型に右渦巻き状の堀を伸ばしていく大拡張計画が立てられました。
この計画により、17世紀中頃の江戸は、約44平方キロメートルもの日本一の巨大都市へと発展します。大都市の京都・大坂でさえ江戸の半分以下の規模で、当時の日本の都市平均面積である約2平方キロメートルと比べると江戸は大変な大きさでした。
そんな江戸も明暦の大火によりたった2日で焦土と化してしまいます。この本には当時の江戸に住む人の生活や文化、今も東京に残る地名の由来なども記されています。
下巻では、明暦の大火後から大政奉還までの約210年間を描いています。災害が起きても「火事と喧嘩は江戸の華」としてたくましく復興しつつ、一方で歌舞伎や浮世絵などの文化を生み出すなど、当時の江戸の町人たちがどういう生活をしていたかがわかる1冊となっています。
太田道灌 室町時代の武将。扇谷(おうぎがやつ)上杉家の重臣で築城術や兵術また和漢の才にも秀でていた。
四神相応 四神は古代中国由来の四方を守護する霊獣(青龍(東)・白虎(西)・朱雀(南)・玄武(北))。四神相応は、その土地の景観が、四神の存在にふさわしい様子であること。東に水の流れ(青龍)、西に大道(白虎)、南に湿地(朱雀)、北に丘陵(玄武)を有する地勢。
