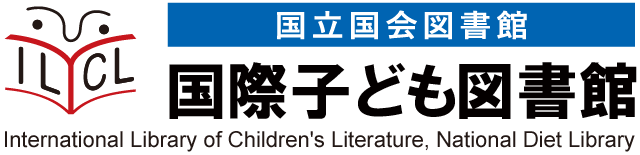児童文学連続講座 平成23年度
児童文学連続講座 平成23年度
総合テーマ「児童文学とことば」
児童文学とは何でしょうか。作者という大人と、読者である子どもがことばによってコミュニケーションをする、あるいは、大人から子どもへ、ことばによって文化を伝達する装置といえるかもしれません。ただ、そのことばについていうと、大人のことばと子どものことばには、大きなへだたりがあります。ことばのへだたりは、思考や感受性の違いにもつながります。児童文学とは、ことばのへだたりを越えて、大人と子どもがコミュニケーションできるかどうかに賭けているジャンルということにもなりそうです。
今回の児童文学連続講座では、「ことば」から児童文学を考え直します。児童文学や絵本とことばのかかわりの問題、そこへさらに、海外の作品の翻訳という問題や、児童文学や絵本の創作の大きな源泉である民話のことばという問題を入れ込んでいくと、この講座は、児童文学というジャンルの存立基盤を根本から問い直す場になるにちがいありません。そして、子どもたちに「ことば」を届ける仕事としての児童サービスについても考え直す場にしたいと思います。
宮川 健郎(みやかわ たけお)
立教大学文学部日本文学科卒、同大学大学院文学研究科日本文学専攻博士前期課程修了。宮城教育大学、明星大学勤務を経て、現在は武蔵野大学教育学部教授。JBBY(社団法人日本国際児童図書評議会)監事。国立国会図書館客員調査員(平成20年度~)。
編著書『きょうはこの本読みたいな』全16巻(共編)、『きょうもおはなしよみたいな』全8巻(共編)、『現代児童文学の語るもの』、『国語教育と現代児童文学のあいだ』、『子どもの本のはるなつあきふゆ』、『名作童話を読む 未明・賢治・南吉』等
平成23年度児童文学連続講座−国際子ども図書館所蔵資料を使って
| 総合テーマ |
「児童文学とことば」 監修 宮川 健郎(武蔵野大学教育学部教授) |
|---|---|
| 開催時期 | 平成23年11月7日(月)、8日(火) |
| 会場 | 国際子ども図書館 ホール(3階) |
| 対象 | 現在、図書館などにおいて児童サービスに従事する方。 1機関1名。定員60名。2日間連続して受講できる方を優先します。応募多数の場合は調整させていただきます。 |
| 備考 | 連続講座の全課程を修了した方に対し、国際子ども図書館長名の修了証書を授与します。 |
講義内容・時間割
総合テーマ 「児童文学とことば」
| 時間 | 内容 | 講師 | 当日配布資料 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 受付開始 | ||
| 9:30-10:10 | 館内見学 | ||
| 10:10-10:20 | 諸注意 | ||
| 10:20-12:00 | 児童文学のことば、児童文学というコミュニケーション | 宮川 健郎(武蔵野大学教育学部教授、国立国会図書館客員調査員) ことばのへだたりを越えて、大人と子どもがどのようにコミュニケーションできるか、千葉省三などの日本の近代童話や、後藤竜二、那須正幹などの現代児童文学の作品を素材に考えていきます。 |
レジュメ(PDF形式:263KB) ブックリスト(PDF形式:288KB) |
| 12:00-13:00 | 休憩 | ||
| 13:00-14:40 | 絵本のことば | 吉田 新一(立教大学名誉教授、元国立国会図書館客員調査員) 絵本における、ことばの表現では、音韻や文体といった、また、テクストでは、その構造といった視点が、考えられますが、限られた時間内ですので、ここではタイポグラフィカルな視点から、絵本のことばについて考察してみましょう。 |
レジュメ(PDF形式:407KB) ブックリスト(PDF形式:315KB) |
| 14:50-15:50 | 参考資料紹介 | 国際子ども図書館職員 | レジュメ(PDF形式:331KB) ブックリスト(PDF形式:335KB) |
| 16:00-17:00 | 意見交換会 |
| 時間 | 内容 | 講師 | 当日配布資料 |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 受付開始 | ||
| 10:00-11:40 | 現代の古典の翻訳—文体と言葉 | 神宮 輝夫(青山学院大学名誉教授、元国立国会図書館客員調査員) J.M.バリの『ピーター・パン』は、1904年に劇として発表され、その後、『ピーター・パンとウェンディ』として1911年に散文化されました。昭和期の翻訳を戦前と戦後で比較してかんがえます。アーサー・ランサム『ツバメ号とアマゾン号』(1930)については、主として訳語の変化、会話などについて説明します。 |
レジュメ(PDF形式:231KB) ブックリスト(PDF形式:338KB) |
| 11:40-12:50 | 休憩 | ||
| 12:50-14:30 | 翻訳絵本のことば | 福本 友美子(翻訳家) 図書館では絵本を選書するとき、必ず対象年齢を考えますが、翻訳者が外国絵本を翻訳する場合も同じ。想定される読者に最もふさわしいことばを選びます。それと同時に原文の流れやリズムをいかに伝えるかを工夫します。講師自身の翻訳した絵本を例に挙げ、読み聞かせも入れながら具体的に解説します。 |
レジュメ(PDF形式:138KB) ブックリスト(PDF形式:283KB) |
| 14:40-16:20 | 民話とことば | 常光 徹(国立歴史民俗博物館教授) 昔話の語りは形式を伴っています。語り 始めるときのことばや、語り手と聞き手のあ いだで交わされる相槌は、伝承される土地 によって変化に富んでいます。講座では、 こうしたことばの意味を考えるとともに、昔話・ 伝説・世間話の特徴について述べます。 |
レジュメ(PDF形式:9KB) ブックリスト(PDF形式:258KB) |
| 16:20-16:30 | 修了証書授与 |
平成23年度児童文学連続講座講義録「児童文学とことば」

※本講義録「児童文学とことば」の印刷版は、社団法人日本図書館協会から発売されています。印刷版の入手に関するお問い合わせは下記までお願いします。
社団法人日本図書館協会
〒104-0033 中央区新川1-11-14
TEL:03-3523-0812(販売直通)
国立国会図書館国際子ども図書館 企画協力課協力係
TEL:03-3827-2053(開館日の9:30~17:00) FAX:03-3827-2043
〒110-0007東京都台東区上野公園12-49
PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。