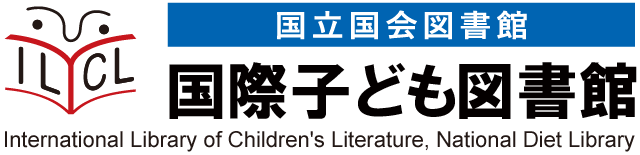児童文学連続講座 令和3年度
総合テーマ「今を生きるヤングアダルトへ」
令和元年度の連続講座「絵本からヤングアダルト文学まで―児童文学基礎講座」では4つの講義のうちの1つとしてヤングアダルト文学を取り上げました。令和2年度はこれを拡大し、「10代に手渡す物語―ヤングアダルト文学総論」と題して連続講座を開催しました。そして、ヤングアダルト文学に光をあてた連続講座の最終年となる今年度は、「今を生きるヤングアダルトへ」というテーマのもと、若者が文学に親しむ意義を考えるという大局的な視点から、具体的な作品の考察、作家と作品の関係、翻訳文学のあり方まで、幅広く扱います。講義1では教育哲学者の苫野一徳氏が若者と文学の出会いと読書法について、講義2では児童文学研究者の白井澄子が困難な現代社会を生きる若者の描かれ方について、講義3では作家のひこ・田中氏がヤングアダルト文学は何を描き出すのかについて、講義4では翻訳家の三辺律子氏が、日本が影響を受けてきた海外文学の翻訳のあり方について語ります。講義5では国際子ども図書館職員が実務に役立つレファレンスサービスを紹介します。講座全体を通して、今後の展望が見えてくることを願っています。
監修 白井 澄子(元・白百合女子大学人間総合学部教授、国立国会図書館客員調査員)
講座概要
| 総合テーマ | 「今を生きるヤングアダルトへ」 |
|---|---|
| 形式 | 動画配信形式(Cisco Webex Eventsを使用) |
| 配信期間 | 2021年11月1日(月)12時~2022年1月11日(火)17時 |
| 参加費 | 無料 |
| 備考 | 修了証書の交付は行いません。 |
講義内容
講義1「“ほんとう”の世界へ ~文学の魅力と、人生に役立つ読書法~」
苫野一徳(熊本大学准教授)
誰もが文学を必要とするわけではありません。でも、文学との出会いは、私たちに、人は「ただ生きる」のではなく、何か“ほんとう”を求め、それに「憧れつつ生きる」ことの喜びを与えてくれます。本講義では、そんな文学の魅力に加え、文学に限らず、私たちの人生を豊かにしてくれる読書法についてお話ししたいと思います。
講義2「現代社会を生きぬく ~ヤングアダルト文学は何をどう映し出す?~」
白井澄子(元・白百合女子大学教授)
若者は家族、友人、学校、地域など社会と関わって生きていますが、時に社会は心地よい関係だけでなく、無理解、対立、疎外感などの痛みを与えることもあります。本講義では、最近クローズアップされている若者の貧困やLGBTなどの性的マイノリティといった問題にも触れながらヤングアダルト文学の意義について考えます。
講義3「ヤングアダルト文学の後先」
ひこ・田中(作家)
ヤングアダルト文学は子ども時代の要請により登場してきました。書き手にとって、それは書くフィールドが拡がったことを意味します。そこでは何がどう描かれ、子どもの本はどのような変化を遂げたのでしょうか?読者にとってどのような意味があるのでしょうか?最後に、今後の展望までをお話しできればと思っています。
講義4「日本の翻訳ヤングアダルト文学の現在」
三辺律子(翻訳家)
かつては翻訳大国と言われた日本ですが、年々海外文学の読者は少なくなっていると言われています。その中で、どのような海外ヤングアダルト文学が紹介されているか、また、その意義とはなにか。具体的な作品を紹介しつつ、探っていきたいと思います。
講義5「児童書に関するレファレンスサービス」
国立国会図書館国際子ども図書館職員
国際子ども図書館のレファレンスで使用する国立国会図書館のデータベースの概要や国際子ども図書館のレファレンス事例をご紹介します。ご紹介する事例は各図書館および18歳以上の方から申し込まれた児童書に関するレファレンスの回答事例です。
講義録
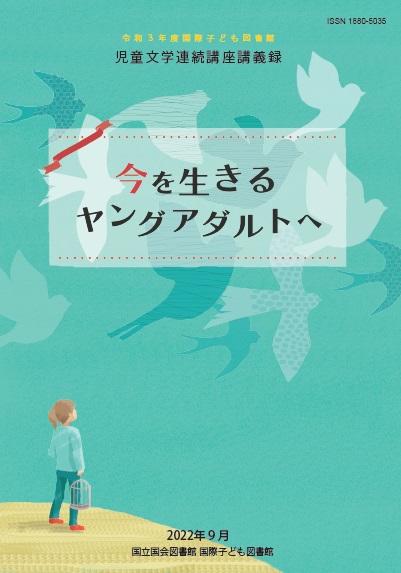
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF版をご覧いただけます。
冊子体は、公益社団法人日本図書館協会から発売されています。冊子体の入手に関するお問い合わせは下記までお願いします。
公益社団法人日本図書館協会
〒104-0033 中央区新川1-11-14
電話:03-3523-0812(販売直通)
国立国会図書館国際子ども図書館 企画協力課協力係
メールアドレス:kenshu![]()
電話:03-3827-2053(開館日の9時30分~17時)
PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。