児童文学連続講座 令和2年度
総合テーマ「10代に手渡す物語―ヤングアダルト文学総論」
ヤングアダルトという言葉がアメリカから入ってきてほぼ40年たち、日本でも定着してきましたが、ヤングアダルト向けの図書の選書や図書館サービスについて、戸惑いや困難を感じている図書館関係者も多いのではないでしょうか。2018年に文部科学省が策定した第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」においては、中高生、特に高校生の「不読率」が話題になり、読書活動の活性化が望まれています。そんな10代の読者に、私たちは何をどう手渡したらよいのでしょうか。今回の講座では、ヤングアダルトを取り巻く状況に目を向け、ヤングアダルト文学に親しむことで、私たちからティーンエイジャーに歩み寄る一歩を踏み出したいと思います。ヤングアダルト文学といっても、現代の日本にはライトノベルという新しいジャンルもありますし、海外ではイラストを多用した小説グラフィックノベルも注目されています。講座では、日本および英米のヤングアダルト文学、ライトノベル、グラフィックノベルについて、また、図書館における活動について紹介をしていく予定です。
講座概要
| 総合テーマ | 「10代に手渡す物語―ヤングアダルト文学総論」 |
|---|---|
| 開催時期 | 令和2年11月9日(月)、10日(火) |
| 形式 | ウェビナー形式(Webex Events を使用) |
| 対象 | 児童サービス担当図書館職員等。各講義定員1,000名程度。 |
| 参加費 | 無料 |
| 接続テスト | 以下の日程で、Webex Eventsへの事前の接続テストを実施。 (日程)
|
| マニュアル | |
| 備考 | 修了証書の交付は行いません。 |
令和2年度児童文学連続講座 概要
講義内容・時間割
総合テーマ「10代に手渡す物語―ヤングアダルト文学総論」
○ 講義1
| 日時 | タイトル及び講師 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月9日(月) 10時~12時 | 「21世紀の英米ヤングアダルト文学―物語がもつ力と危険性」 水間 千恵(川口短期大学教授) | メディアの多様化が進むいま、読書という形で物語世界を体験することの意味を、英米ヤングアダルト作品を例に考察します。同時に、普段見落とされがちな、物語がもつ負の側面にも目を向けたいと考えています。 |
○ 講義2
| 日時 | タイトル及び講師 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月9日(月) 13時30分~ 15時30分 | 「ヤングアダルト書籍としてのライトノベル」 大橋 崇行(東海学園大学准教授) | 図書館ではヤングアダルトコーナーに排架されることが多いライトノベルですが、シリーズを買い続けることの難しさや、性的な表現の介入、流行の期間が短いこと、多様な作品の刊行など、さまざまな問題を抱えています。本講座では、それらの問題について、子どもたちと本との関わり方という視点から、考えていきたいと思います。 |
○ 講義3
| 日時 | タイトル及び講師 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月9日(月) 16時~16時40分 | 「国際子ども図書館の中高生向けサービス」 国立国会図書館国際子ども図書館職員 | 国際子ども図書館の「子どもと本をつなぐ」ための様々な取組のなかから、リニューアル後の平成28年から開始した中学生・高校生向けのサービスをご紹介します。 |
○ 講義4
| 日時 | タイトル及び講師 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月10日(火) 10時~12時 | 「現代日本児童文学と「ヤングアダルト文学」」 奥山 恵(児童書専門店経営、白百合女子大学非常勤講師) | 日本でヤングアダルト文学という用語がひろまってきた経緯を、「ヤングアダルト出版会」「朝の読書」といった出版や読書運動の動き、また「タブーの崩壊」「ボーダーレス」といった関連する日本児童文学の動きとともに整理し、具体的に中高生以上の読者にすすめたい日本の作品について考えます。 |
○ 講義5
| 日時 | タイトル及び講師 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月10日(火) 13時30分~ 15時30分 | 「英語圏のヤングアダルト文学と図書館活動」 白井 澄子(白百合女子大学教授、当館客員調査員) | 英語圏ではどのようなヤングアダルト(YA)文学が書かれ、読まれているのでしょうか。初期の問題小説から現代のグラフィックノベルまでを概観し、扱われるテーマや表現の変化、読者の反応についてお話しします。また、今、どのようなYAサービスが必要とされ、実際に実践されているかについても紹介したいと考えています。 |
講義録
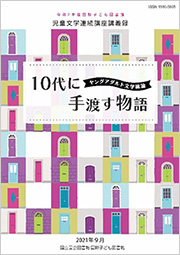
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF版をご覧いただけます。
冊子体は、公益社団法人日本図書館協会から発売されています。冊子体の入手に関するお問い合わせは下記までお願いします。
公益社団法人日本図書館協会
〒104-0033 中央区新川1-11-14
電話:03-3523-0812(販売直通)
お問い合わせ先
国立国会図書館国際子ども図書館 企画協力課協力係
メールアドレス:kenshu![]()
電話:03-3827-2053(開館日の9時30分~17時)
PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。![]() >> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)