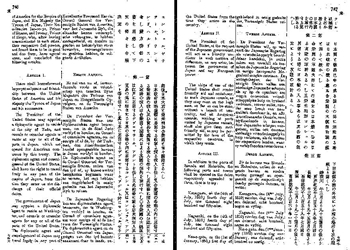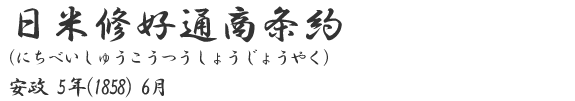 日米修好通商条約
日米修好通商条約
(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく)
安政5年(1858)6月
史料の背景
孝明天皇(こうめいてんのう)からは条約調印の勅許が得られないまま、安政5(1858)年6月19日、大老井伊直弼(いいなおすけ)は「日米修好通商条約」全14条(付属貿易章程7則)を締結しました。条約の調印は神奈川沖に泊まっているポーハタン号の上で行いました。
また幕府は、アメリカに続いて、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同様の条約を結びました。これを安政の五か国条約といいます。
いずれも、関税自主権(かんぜいじしゅけん)を欠き、治外法権(ちがいほうけん)を認める不平等条約で、後に明治政府が力を入れて欧米諸国と交渉を行うことになる条約改正の課題となりました。
なお、条約の調印場所となったポーハタン号は、日米修好通商条約の批准書 【批准書】
条約に対する国家の確認・同意を示す文書。
この文書の交換または寄託によって条約の効力が生じる。 を交換するため、安政7(1860)年1月、アメリカに向けて横浜を出発しました。勝海舟(かつかいしゅう)らが乗る咸臨丸(かんりんまる)も共にアメリカに向かいました。
| 注1: | 【批准書】 | 条約に対する国家の確認・同意を示す文書。 この文書の交換または寄託によって条約の効力が生じる。 |
史料を読んでみよう
第四条では、アメリカとの貿易品にかかる税(関税、史料では「運上」)の割合(税率)は日本とアメリカがお互いに協定して決めることが定められています。税率の決定権が日本になく、関税自主権の欠如となる不平等な条約でした。
第五条では、外国の貨幣と日本の貨幣とを今後1年間交換できることが決められました。また、金貨・銀貨の輸出も認められていました。しかし、貨幣に含まれている金や銀の量が、日本と外国とでは異なるため、日本の金貨が大量に海外へ持ち出されることになりました。
このため、貿易が正しく発展できないと心配したハリスらは、幕府に金貨の改鋳(かいちゅう、作り直し)を求め、万延(まんえん)元(1860)年には金貨の改鋳を行い、金貨の流出は止まりました。
第六条では、日本に滞在するアメリカ人が罪を犯した場合は、領事裁判所でアメリカの法律により裁かれることが書かれています。これは実質的に治外法権を認める内容で、第四条と併せて日本に不平等な条約でした。
第七条では、第三条で決めた開港場所付近のアメリカ人の行動範囲を規定しています。例えば、神奈川港では、六郷川(ろくごうがわ)沿いを境とし、そのほかの方角は約十里までと決めました。文久2(1862)年に起こった生麦事件 【生麦事件】
薩摩藩の島津久光(しまづひさみつ)が国元の薩摩に帰る途中の行列を横切った騎乗のイギリス人を藩士が殺傷した事件。 は、日英修好通商条約で同じようにイギリス人の行動範囲が規定され、その範囲内にある生麦村で起きました。
| 注2: | 【生麦事件】 | 薩摩藩の島津久光(しまづひさみつ)が国元の薩摩に帰る途中の行列を横切った騎乗のイギリス人を藩士が殺傷した事件。 |
参考文献
| :児童書 | :小説 |
平川南〔ほか〕編 大石学著『Jr.日本の歴史.5』
小学館 2011 【Y2-N11-J89】
安田常雄監修『日本の歴史.4』(ポプラディア情報館)
ポプラ社 2009 【Y2-N09-J157】