全面開館記念行事を行いました。イベント
2002年5月4日
国際子ども図書館全面開館記念行事
2002年5月4日、快晴の日に国際子ども図書館全面開館記念行事が行われました。
国際子ども図書館は、2000年に部分開館をしていましたが、その後も改修工事を行い、この日、全てをご覧いただくことができるようになりました。


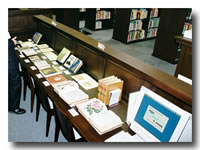


国立国会図書館国際子ども図書館
開館10周年及び国民読書年記念展示会
 Children's Books Going Overseas from Japan
Children's Books Going Overseas from Japan
2002年5月4日
国際子ども図書館全面開館記念行事
2002年5月4日、快晴の日に国際子ども図書館全面開館記念行事が行われました。
国際子ども図書館は、2000年に部分開館をしていましたが、その後も改修工事を行い、この日、全てをご覧いただくことができるようになりました。


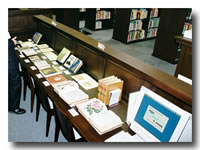


2002年5月5日

国際子ども図書館は2002年5月5日に全面開館しました。
日差しの強い中、多数の利用者の方々にご来館いただきました。
今後とも、国際子ども図書館をよろしくお願いいたします。
2002年5月11~12日、18~19日、25~26日、6月1日
2002年5月25日

新潟にお住まいの、高橋ハナ刀自※に昔話をしていただきました。
当日は、小さなお子様から昔を懐かしむ年配の方まで様々な方が、各回80人ほど参加しました。
「三枚のお札」「鳥呑み爺」「山伏とキツネ」「和尚と小僧」などのお話をしていただきました。
(※「刀自(とじ)」とは、社会から尊敬されている、高年の婦人に対する敬称です。)
2002年7月8日

国際子ども図書館全面開館記念シンポジウム
「昔話から物語へ」
場所:東京国立博物館平成館大講堂
国際子ども図書館では、2002年7月8日(月)、東京国立博物館平成館大講堂において、全面開館記念シンポジウム「昔話から物語へ」を開催しました。今回のシンポジウムは、全面開館記念展示「不思議の国の仲間たち―昔話から物語へ」のテーマに関連し、「今の子どもたちに伝えたいもの」を共通のキーワードとして、内外の五人のパネリストに語っていただきました。
シンポジウムには定員を超える申込みがあり、当日は257名もの参加者が、パネリストの報告に耳を傾けました。参加者には、図書館関係者のほか、伝承文学を研究する学生、おはなしボランティアの方々も目立ち、一般の方も多数参加しました。
第一部は、国立国会図書館長戸張正雄(当時)による開会の挨拶で始まり、国際子ども図書館長富田美樹子の司会で、各パネリストからの報告が行われた。
司会・富田美樹子(国際子ども図書館長)
[報告]
野村純一氏(國學院大學教授) 「昔話と「絵」」
崔 仁鶴氏(仁荷大学校名誉教授) 「韓国における昔話から児童文学へ」
神宮輝夫氏(青山学院大学名誉教授)「昔話から創作へ―20世紀後半の日本を中心に」
たつみや章氏(作家)「血の中に流れる母国文化に気づいて」
シビル・A・ヤーグシュ氏(米国議会図書館児童書センター長)「現代の子どものための昔話と妖精物語」
質問票に基づく、話の展開
閉会の辞・富田美樹子
2002年7月9日
国際子ども図書館全面開館記念シンポジウムの講師として来日された、米国議会図書館児童書センター長シビル・A・ヤーグシュ博士に、アメリカの子どもの本の中に描かれてきた日本の姿を19世紀半ばから今日までの流れに沿って紹介していただきました。
2002年7月27日

[講師]塚原 博 氏(東京学芸大学講師、科学読物研究会会員)
[開催日時]
「よわいかみつよいかたち」7月27日(土) 午後2回
「風船の不思議」7月28日(日) 午後2回
ハガキや風船など、身近な材料を使って科学遊びを楽しみました。
始めに塚原先生が、実験の説明をして、子どもたちにその結果を予想させると、いろいろな予想や意見が飛び出してきます。実際にやってみると全く違った結果が出て、子どもたちは驚いたり、やり方を工夫したりしていました。
その後、子どもたちが科学に本に親しむきっかけになるようにと、この日にやった科学遊びの本を紹介して終了しました。
2002年8月3日
[講師]栗木 衛 氏(経師)
参加した子どもたちみんなが、一本の道でつながるように描いた絵を貼り合わせて、33mという長い絵巻を作りました。
栗木先生に和装本の見本を見せてもらいながら、本の形の歴史についてのお話を聞いたあと、1人1枚ずつ和紙に絵を描き、刷毛でのりをつけ貼り合わせました。
軸や表紙裂もついて完成した絵巻は、8月13日から9月1日までエントランスで展示しました。


2002年8月20日

8月19日から25日まで、東京・兵庫・大阪・奈良を移動しながら、童話・絵本を通じて日中韓の子どもたちがお互いの文化を理解し合うための交流事業が行われました。その結団式が20日午後当館を会場として開催され、小泉首相(当時)をはじめとする多数の来賓が出席しました。この行事には、中国と韓国から25名ずつ、日本から42名の計92名の小学生が参加し、結団式終了後、当館の見学および、『おおきなかぶ』の日中韓3か国語による群読が行われました。
2002年10月5日

「子どもたちのまなざし-アボリジニの大地から-」展の関連行事として、カメラマン永武ひかるさんの講演会が行われました。講演では、アボリジニの方々のキャンプに参加されたときの体験、子どもたちとの出会い、彼らの生活や文化、学校について写真を交えて紹介していただきました。
2002年11月2日、10日
「子どもたちのまなざし―アボリジニの大地から―」展にあわせて、アボリジニの民族楽器で、世界最古の管楽器であるディジュリドゥをテラスにて井上隆広さんに演奏していただきました。演奏会が行われた2日間は、若干肌寒い天候でしたが、多くの方が参加し井上さんの演奏に耳を傾けました。また、子どもを含むほとんどの参加者が初めてのディジュリドゥ演奏に挑戦する姿が印象的なイベントとなりました。演奏会の最後には参加者全員で井上さんとセッションを行いました。
2002年11月20~22日
当館の広報を行うために、会場内でパンフレットの配布等を行いました。
2002年12月16日
「絵本に見る夢-ヨーロッパの国々から-“Europe, a dream in pictures?”」展に関連し、ヨーロッパ絵本の専門家であり、今回の展示資料をお借りしたフランスのシャルル・ペロー国際研究所の研究グループの一員であるSophie Van der Linden氏とフランス児童文学研究・翻訳家の末松氷海子氏を迎えて、講演会を開催しました。
この講演会は、ヨーロッパの絵本の動向を専門家の立場から紹介していただき、展示会への一層の理解を深めてもらうために開催しました。当日は、参加者から意見や質問が多数寄せられました。